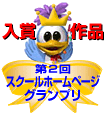食品添加物
食品添加物にはどんなものがあるのか、必要なのか、安全性はどうなのかについて考えてみましょう。

食品添加物
01 はじめに
私たちは,毎日欠かさず食事をします。これは当然私たちが健康的に生活するために絶対必要なものです。したがって,栄養バランスがよく,安くて,美味しいのが理想的な食品です。最近では,加工食品の種類も多くなり,手軽に美味しい料理が食べられるようになりました。冷凍食品,レトルト食品,インスタント食品などの加工食品のおかげで私たちの食生活が便利で楽しいものになったことは言うまでもありません。こんな便利な加工食品を作るためには食品添加物が必要なのですが,この食品添加物は非常に評判が悪く,「発がん性がある」,「アレルギーになる」などとまるで毒物のような扱いを受けています。それでは,この食品添加物は本当に毒物なのでしょうか?

私は,製薬メーカーの研究所に約10年ほどいましたが,「薬(化学的合成品)=発がん性,アレルギー性」といって騒いでいる患者さんをあまり見たことがありません。一方,同じ化学的合成品でも食品添加物は「食品添加物(化学的合成品)=発がん性,アレルギー性」といって騒がれるわけです。食品添加物も医薬品と同じように安全性のチェック十分に行われていますし,違��うのは薬は作用が出る量(比較的大量)を服用しますが,食品添加物は作用が出ない量(ごくわずか)を摂取するということぐらいです。この食品添加物,本当に危険なものばかりなのでしょうか。
インターネット上で毒物として騒がれている食品添加物のなかに,「これは少し過剰反応では?」とおもわれるものがいくつかありました。ここでは,食品添加物の安全性について皆さんに正しく理解していただくために,食品添加物を少し勉強することにしましょう。
02 食品添加物がなかったら
スーパーマーケットには,様々な食品が所狭しと並べられています。これらの食品のうち食品添加物が使われているものをすべて店頭から取り除いたらどうなるでしょう。お惣菜や揚げ物,豆腐,漬け物,お弁当なども調味料,着色料,豆腐凝固剤,増粘剤,発色剤,酸化防止剤,保存料などが使用されているためほとんど取り除かれます。さらに進んで,海老フライやハンバーグなどの冷凍食品には,調味料,酸味料,膨張剤,乳化剤,着色料など,アイスクリーム,プリン,ヨーグルトなどの乳製品には酸味料,乳化剤,香料,安定剤,着色料などの添加物が使用されています。さらに,コーラ,果汁飲料などの清涼飲料水には,酸味料,甘味料,保存料,酸化防止剤,香料,着色料が含まれています。チョコレートやポテトチップス,キャンディーなど菓子類,ハム,ソーセージなどの食肉加工品,砂糖,しょうゆ,みそ,ソースなど調味料,漬け物,缶詰といったもののほとんどに食品添加物が使われています。

さて,残ったものは,緑色で示した野菜,果物,刺身,鮮魚,精肉,牛乳などです。しかし,果物でも外国から輸入されたグレープフルーツやバナナなどには防かび剤が使用されていますので,3分の1ぐらいは取り除かれます。こうして見てみると,スーパーマーケットに並んでる食品のほとんどに食品添加物が使用されていることがわかります。
03 食品添加物の分類
一般に,「合成」であるか「天然」であるかが食品添加物の良否を決めるキーワードになっていました。しかし,本来の「安全」は,「天然=安全,合成=危険」というイメージではなく,科学的に安全であるかどうかが大切なのです。
平成7年の食品衛生法改正により,発がん性試験など安全性試験を実施して安全性が確保されているものと使用実績はあるが,必ずしも安全性の根拠となるデータが存在しないものに分類されました。
すなわち,食品衛生法により厚生労働大臣が安全性や有効性を確認して指定した「指定添加物」,天然添加物としてすでに使用実績のある「既存添加物」,長い食経験のある「天然香料」,「一般に食品として飲食に供されているものであって添加物として使用されている品目(一般飲食物添加物)」に分類されます。

04 指定添加物
食品添加物として指定されるためには,「人の健康を損なうおそれがなくかつその使用が消費者に何らかの利点を与えるもの」でなければなりません。「食品添加物として指定されるための基本的考え方」にしたがって審査され,その必要性が明確になったものだけが食品添加物として認められます。「味や風味をごまかす」「粗悪な素材で加工食品を製造する」などの理由で使用が許可される食品添加物はありません。

食品添加物の指定にあたっては,内閣総理大臣あてに食品添加物の成分規格,使用基準,安全性などに関する多くの資料を揃えて提出しなければなりません。安全性関しては反復投与毒性試験,発がん性試験,繁殖試験や微生物,培養細胞などを使った様々な試験をして,安全性を科学的に証明しておく必要があります。特に,発がん性試験は最も大事な試験で,もしこの試験で「陽性」と判定されたものは基本的に食品添加物として使用されることはありません。これらの試験を実施するために,数億円〜数十億円の費用がかかります。
食品添加物として認められるためには,医薬品と同レベルの安全性試験をクリアしないと認められないということです。



05 既存添加物
「既存添加物」は,以前天然添加物として使用されていたもので,平成7年5月24日の時点でわが国ですでに使用されており,長い食経験?のある489品目については,引き続き��食品への使用や販売が認められることになりました。しかし,安全性に問題があるとされたものについては,使用するべきではなく,また使用実態のない既存添加物についても既存添加物名簿から消除することとなりました。現在,厚生労働省が中心となって既存添加物の安全性に関する見直しが順次行われています。


「既存添加物」の安全性は,FAO/WHO合同食品添加物専門家会議(JECFA)においても評価されています。よく見かける「既存添加物」の安全性を調べてみましょう。
【評価基準】
・特定しない・制限しない:食品に存在する成分,食品とみなされるもの,ヒトの代謝物とみなされるもので,極めて毒性の低い物質
・ADI設定せず:データが十分になく未評価あるいは食品添加物としての使用が不適当なもの
・現在の使用を認める:現在の特定用途および摂取量での使用は毒性学的に問題はないと考えられるもの

過去に天然添加物として使用されていたもの(489品目)のうち,安全性に問題のあるものや使用実績のないものは削除され,現在の既存添加物(365品目)はほぼ安全性に問題はないものと思われますが,コチニール色素はアレルギーを誘発する可能性が報告されていますので,注意が必要です。
06 食品添加物の1日摂取量
食品添加物の実際の摂取量を把握することは、食品添加物を安全かつ適正に使用するためには重要な情報となります。厚生労働省では、マーケットバスケット方式を用いた食品添加物一日摂取量調査を実施しています。マーケットバスケット方式とは、スーパーマーケット等で販売されている食品中に含まれる食品添加物量を測定し、得られた結果に国民栄養調査に基づく喫食量を乗じて摂取量を求めるもので、その結果は厚生労働省ホームページから情報提供されています。
ここでは、加工食品に含まれる食品添加物のうち、分析法が確立されている指定添加物の含有量について掲載しました。なお、既存添加物は混合物であったり、分析法が確立されていないことから1日摂取量調査はできません。
平成9年〜令和元年の厚生労働省による食品添加物の摂取量調査から食品添加物の一日摂取量は、8355mg/人/日となりました。このうち、最も摂取量が多かったのがビタミン・ミネラル・アミノ酸など栄養強化剤(2455mg/人/日)であり、次いでクエン酸、酢酸、」乳酸などの酸味料(2101 mg/人/日)、アミノ酸や核酸などの調味料(1710 mg/人/日)の順でした。ただし、これらの食品添加物は、いずれも食品や生体にも含まれる成分であることから、ここで示された摂取量には正味の食品添加物摂取量に加え、原材料となる食品に由来する成分も含まれています。

07 甘味料 スクラロース
【概要】
スクラロースは、ショ糖(砂糖)から作られる甘味料で、ショ糖の砂糖の600倍の甘味度をもつ甘味料です。
1970年の中頃に、ショ糖の甘味を高める研究が活発に行われた結果、ショ糖のヒドロキシ基のうちの3つが塩素で置き換わった構造を持つスクラロースが発見されました。
1991年にカナダにおいてスクラロースを甘味料として使用することが許可され、その後アメリカ(1999年)、日本(1999年)、EU(2004年)でも使用が許可されました。
近年炭酸飲料やスポーツドリンクなど清涼飲料水を中心に、広く利用されています。
【安全性】
急性毒性、慢性毒性、生殖発生毒性、遺伝毒性等が実施され、いずれも毒性となる所見は認められていません。特に、発がん性については、マウスおよびラットを用いた2年間の試験が行われていますが、腫瘍発生の頻度は増加しませんでした(Mann et al., Food Chem.Toxicol. 38(Suppl.2) S71-89, 2000a、Mann et al., Food Chem.Toxicol. 38(Suppl.2) S91-98, 2000b)。
【代謝】
摂取されたスクラロースは、摂取後5日間で、未変化のままその78%が糞便中に排泄され、14.5%が尿中に排泄されます(Roberts et al., Food Chem.Toxicol. 38(Suppl.2) S31-41, 2000)。また、長期間にわたって接種しても、体内への残留や蓄積はなく、腸内細菌に影響を与えません(Sims et al., Food Chem.Toxicol. 38(Suppl.2) S115-121, 2000)。このように、摂取されたスクラロースのほぼ全てが体内を通過するだけです。
【一日摂取許容量(ADI)】
上記の結果などにより、スクラロースの一日摂取許容量(ADI)は、15mg/kg体重/日、879mg/人(日本人平均体重58.6kg)/日と設定されてます。
最新の調査では、日本人のスクラロースの1日摂取量は、0.752mg/人/日であり、1日摂取許容量の0.09%と大きく下回っています。
【MOTTO!食品衛生からのコメント】
安全性が十分に確保されているスクラロースですが、次のような危険性を指摘する方がいらっしゃいます。
Q1. 構造に「塩素」を含むから、体内で有害な「塩素ガス」が発生するのではないか。
A1. スクラロースは、砂糖(スクロース)のヒドロキシ基のうちの3つが塩素で置き換わった構造を持っています。摂取されたスクラロースは、摂取後5日間で、未変化のままその78%が糞便中に排泄され、14.5%が尿中に排泄されます。このように、摂取されたスクラロースのほぼ全てが体内を通過するだけですので、「体内」で「塩素ガス」が発生することはありません。体内には、大量の「塩化物イオン」は存在しますが、それが「塩素ガス」になることはありません。そんなことがあったら食塩(NaCl)なんか食べられません。1日に食塩(11g)から摂取する塩素は男性で平均6700mg、スクラロース(0.01g、6gのショ糖に相当)から摂取する塩素は2.6mgですから、塩素を問題にするのならどちらかは一目瞭然ですよね。
ただし、スクラロースやスクラロースを含む「食品」を120℃を超えて加熱し続けると有害となる有機塩素化合物が生成する懸念があると指摘されています(ドイツ連邦リスク評価研究所)。現時点では、加熱の際に生成される副産物や生成量に関するデータが不足していることから、さらなる研究が必要です。

詳細版
08 甘味料 アセスルファムカリウム
【概要】
アセスルファムカリウムは、砂糖の約200倍の甘味度を持つ非栄養性甘味料であり、その安定性とカロリーゼロの特性から、世界100カ国以上で4000品目以上の食品・飲料に使用されています。
1967年、ドイツのヘキスト社(現:Nutrinova GmbH)の研究者カール・クラウスによって、オキサチアジノンジオキシド誘導体の研究中に偶然発見されました。その後、安全性が評価され、米国では1988年に米国食品医薬品局(USFDA)によって食品添加物として承認されました。現在では、EU、カナダなど世界100カ国以上で承認され、日本では2000年4月25日に食品添加物として指定されました。
【安全性】
安全性は、JECFA(FAO/WHO合同食品添加物専門家会議)などの国際機関によって厳格に評価されていて、ラットを用いた2年間の反復投与毒性試験で得られた無毒性量(NOAEL)1500mg/kg体重/日を基に、安全係数100を適用した一日摂取許容量(ADI)0~15mg/kg体重/日が設定されています。 急性毒性、慢性毒性、生殖発生毒性、遺伝毒性等が実施され、いずれも毒性となる所見は認められていません。
日本の厚生労働省による調査では、実際の国民の一日摂取量は、1.779mg/人/日で、ADIの0.20%程度と極めて低い水準になっています。
【体内動態】
ヒトにおいて経口摂取後、速やかにかつほぼ100%吸収されます。 服用後1~1.5時間で最高血中濃度に達し、血中半減期は約2.5時間です。ヒトの体内では代謝されず、摂取後24時間以内に97.5〜100.0%が未変化体のまま尿中に排泄されます。
【MOTTO!食品衛生からのコメント】
2013年に発表されたマウスを用いた40週間の長期投与研究では、空腹時インスリンおよびレプチン値の変化といった軽微な代謝への影響に加え、学習・記憶能力の低下が報告されています。この認知機能障害は、海馬における神経代謝機能の変化と関連している可能性が示唆されており、アセスルファムカリウムの長期的な中枢神経系への影響については、さらなる研究が必要です。
環境科学の問題としては、アセスルファムカリウムの高い水溶性と低い分解性から、当初は環境中に残留しやすい物質と考えられていました。しかし、2014年頃から、アセスルファムカリウムを効率的に生分解できる微生物の存在が報告されるようになり、除去率が90%以上に達する事例も確認されています。したがって、アセスルファムカリウムの環境リスクは無視できるレベルであると考えられます。
日本国内では、食品添加物全般、特に「人工」「合成」といった用語に対して、消費者が漠然とした不安感を抱く傾向があります。これに応える形で「無添加」「不使用」といった表示が広く用いられてきましたが、科学的根拠に乏しく、消費者に誤認を与える可能性があるとして問題視されました。この結果、消費者庁は2022年3月に「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」を策定し、「人工甘味料不使用」などの表示が消費者の誤認を招くおそれがあるとして、事業者に自己点検を促しています。
09 保存料 ソルビン酸・ソルビン酸カリウム・ソルビン酸カルシウム
【概要】
ソルビン酸の抗菌作用は1939年から1940年にかけてドイツとアメリカで発見されました。日本では1955年に食品添加物として指定され、ソルビン酸カリウムは1960年、ソルビン酸カルシウムは2010年に指定されました。ソルビン酸は、水に溶けにくいため、水に溶けやすいソルビン酸カリウムが広く利用されています。
ソルビン酸は、脂肪酸の一種であり、カビ、酵母、細菌類に対して広い抗菌スペクトルを持つことで知られています。その作用は、微生物の発育を阻止する静菌作用であり、特にpHが低い酸性条件下で非解離分子の割合が増加し、その効果が増大する特性を持ちます。ソルビン酸には、殺菌効果はありません。
作用のメカニズムは、微生物の細胞膜を透過し、細胞内の脱水素酵素系の作用を阻害することで微生物の発育を抑制します。
【用途】
魚肉練り製品、食肉製品、漬物、ジャム、フラワーペースト、チーズなど、多岐にわたる食品の保存に使用されています。
【安全性】
安全性については、広範な科学的試験に基づき、国際的に高い評価を得ています。FAO/WHO合同食品添加物専門家会議(JECFA)によって設定された一日摂取許容量(ADI)は、ソルビン酸として0~25mg/kg体重/日であり、これは動物実験で有害な影響が見られなかった最大量(無毒性量)に100倍の安全係数を考慮した値です。日本のマーケットバスケット方式による調査では、実際の国民一人当たりの摂取量はADIを大幅に下回る約0.3~0.5%程度と報告されており、安全マージンは極めて大きくなっています。
【体内動態】
生体内では、ソルビン酸は通常の脂肪酸と同様に代謝され、最終的に二酸化炭素と水に分解されます。発がん性は認められておらず、遺伝毒性についてもほとんどの試験で陰性結果が示されています。日本では1955年に食品添加物として指定されて以来、チーズ、魚肉練り製品、ジャム、漬物など多岐にわたる食品の保存性向上と食中毒リスク低減に貢献しています。その使用は食品衛生法に基づき、対象食品ごとに厳格な使用基準が定められています。
【MOTTO!食品衛生からのコメント】
ソルビン酸をはじめとする食品添加物は、科学的根拠に基づき安全性が確保されているにもかかわらず、「化学物質=危険物」という漠然とした不安を持つ消費者が依然として存在します。たとえば、「微生物が死ぬような合成保存料は人間にも危ない」という主張は、代謝能力の違いを無視した誤解です。微生物はソルビン酸を分解できないため、少量でも生育が阻害されますが、人間は脂肪酸として速やかに分解できるため、基準値内の摂取では全く問題となりません。